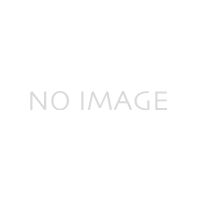2025年4月6日、全国の高速道路で発生したETCの通信障害。
通過できない、バーが開かない、誤請求が起こる――普段当たり前に使っていたシステムが一瞬にして「不便の象徴」となりました。
この出来事は、ただの一時的トラブルではなく、私たちの社会インフラに潜む見えない構造の歪みを浮かび上がらせています。
ETCとは何か?そして、なぜ日本だけが取り残されつつあるのか。
ETC(Electronic Toll Collection)は、日本では2001年から全国統一で導入された、自動車の高速料金を非接触で支払える画期的なシステムです。
車載器とETCカードを組み合わせ、料金所をノンストップで通過できる仕組み。これによって渋滞は大幅に削減され、利用者にも利便性をもたらしました。
しかし、その一方でこう思ったことはありませんか?
-
「車載器を買うのが面倒」
-
「レンタカーや外国人旅行者はどうするの?」
-
「ETCカードって結局クレカ依存…?」
そう、ETCは万能ではありません。むしろ、**すでに時代遅れになりつつある日本独自の“ガラパゴスシステム”**になってしまっているのです。
海外の道路はもっと自由で、もっとスマート。
実は、世界の多くの国ではETC車載器が不要な仕組みが主流です。
たとえばアメリカでは、ナンバープレートをカメラで読み取って、後日クレジットカードで支払う「Toll-by-Plate」方式が広く普及。
E-ZPassやSunPassといった州独自の電子タグもありますが、車載器がなくても支払いが可能な柔軟設計です。
ヨーロッパでは国ごとにビネット(定額料金ステッカー)制度があったり、スマホでナンバーを登録してオンライン決済できたりと、多様な仕組みが共存。
そして中国では、スマホアプリでETC管理が当たり前。アリペイやウィーチャットペイと連動し、キャッシュレス・カードレス社会を実現しています。
それに比べて、日本のETCはどうでしょうか?
なぜ日本は車載器が必要なのか?そこに潜む「利権」という壁。
日本のETCが普及する過程で、車載器を扱う企業、システム開発を請け負う企業、関連団体に莫大な予算が流れ込んできたことはあまり知られていません。
その中心にいたのが、財団法人「ITSサービス高度化機構」――国交省OBが多数天下っている組織です。
ETC関連機器の認証業務、キャンペーン推進、車載器購入補助金の配布など、利権の温床とも言える構造が何十年も続いてきたのです。
4月6日の不具合も、特定の企業や団体が「独占的に管理」してきた構造が、システム障害の原因を複雑化させたという見方もできます。
国民にとっては、「利便性」を掲げながら、一部の既得権益を守るためのシステムになっていたのではないでしょうか。
これからの日本に必要なのは、「規制緩和」と「選べる自由」
このままでは、EVシフトや観光立国戦略、カーシェアの成長にもブレーキをかけてしまいます。
私たちが目指すべきは、「車載器がなくても」「スマホだけでも」「旅行者でも」簡単に使えるスマートな課金システムです。
そのためには――
✅ ナンバー認識による自動課金(Toll-by-Plate)の導入
✅ スマホアプリによる事後決済機能
✅ ETCカード以外の支払い手段(QR決済、プリペイドなど)の許容
✅ 中央管理からの脱却と地方自治体や民間との連携
✅ そして、既得権益の構造を見直す真の規制改革
これが進まなければ、日本の道路は**見えない料金ゲートで縛られた“デジタル封建制度”**のままです。
仁藤流・住宅から見える「社会の構造」とその先
私たちは普段、家づくりというフィールドで「快適」「健康」「災害に強い」といった未来の暮らしを創っています。
でもその周辺――たとえば「道路」「移動」「課金」といった仕組みが旧態依然としていたら、本当に持続可能な社会とは言えません。
社会を構成する「仕組み」そのものに、疑問を持つこと。
それは、「より良い家を建てる」こととまったく同じなのです。
最後に──「通れないゲート」が私たちに教えてくれたこと
4月6日、日本中で起こったETCの不具合は、一瞬にして何千人もの運転手の足を止めました。
しかしその“通れないゲート”は、私たちが本当に進むべき未来へのヒントを静かに示してくれていたのかもしれません。
便利とは、誰かの利権のためではなく、みんなの自由のためにあるもの。
明工建設はこれからも、社会のしくみに対しても問いを投げかけながら、家と暮らしの未来をともに考えていきます。
ご縁を大切に唯一無二の家造り
おかげさまでありがとうございます。